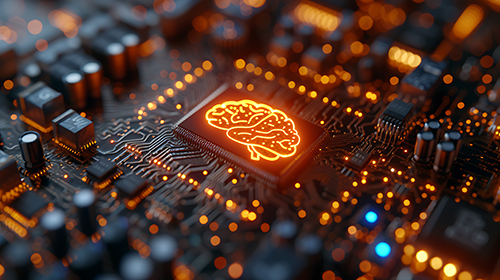近年、生成AIや自然言語処理を活用したサービスがぞくぞくと登場しています。
社内業務の効率化から顧客向け接客、自動応答、文書処理まで、AIを活かせる場面はどんどん広がっています。
AIを活用したサービスの特徴が知りたい、ほかのサービスとの違いがわからないなど、サービスを検討している人に対して、効果的にアピールする動画をあつめました。
目次
1)おもてなしQRメーカーデモ動画
2)Slack AI が登場!新しい生成AI機能で、毎日の仕事をさらにスピーディーに|Salesforce
3)IVRyサービス紹介|電話DXはIVRy(アイブリー)
4)AI Assistant: PDF AI tools from Adobe Acrobat
5)「要約」のAIは、「要約」のためだけじゃない|ELYZA ブランドムービー
まとめ
1.おもてなしQRメーカーデモ動画
この動画では、「おもてなしQRメーカー」が QR コードにアクセスしたユーザーに対して、多言語の音声+字幕付き動画を提供する仕組みをデモしています。
実際には、日本語で入力した内容が即座に英語や中国語などに翻訳され、音声付き動画として閲覧可能になる様子がわかります。
動画作成を検討する人にとって注目すべき点は、QR コードを差し替えることなく中身を更新できる運用設計と、翻訳+字幕生成を自動化するプロンプト設計・AIパイプラインの流れです。
実地利用を想定して、観光案内や店舗案内など変化が頻繁な情報を扱う現場で、更新コストを抑える構成が見える点が魅力です。
2.Slack AI が登場!新しい生成AI機能で、毎日の仕事をさらにスピーディーに|Salesforce
Slack に追加された生成 AI 機能(スレッド要約、AI検索など)を紹介する動画です。
チーム内コミュニケーションを取りながら、過去のメッセージを瞬時に検索したり、議論の流れを要約させたりするシーンが示されます。
動画作成視点での注目ポイントとしては、デモ→実利用フローを見せることで、どのような操作によって何が変わるかをわかりやすく伝えている点です。
さらに、UI操作を追いやすい画面キャプチャや拡大表示の使い方が参考になります。
とくに、Slack の UI に AI 機能を溶け込ませて「違和感なく動く」様子を見せられている点は、サービス紹介動画でも説得力を高める手法として使えます。
3.IVRyサービス紹介|電話DXはIVRy(アイブリー)
この動画では、IVRy が提供する「電話応答の自動化」機能を紹介しています。
着信応答から用件振り分け、折返し案内までを AI が担う流れがイラストと実演で表現されています。
実際の通話フローを可視化するアニメーションが挿入されていたり、ユーザーの操作レスポンス感を示す演出を丁寧に入れたりしていることで、サービスのメリットを伝えています。
AIの対応がどのくらいの反応速度なのかを伝える演出になっており、サービスへの信頼感が増す構成といえます。
4.AI Assistant: PDF AI tools from Adobe Acrobat
Adobe Acrobat に統合された AI Assistant 機能を、PDF 文書の要約や質問応答、編集支援などの観点から紹介する動画です。
実際の PDF を読み込んで質問したり、要約を出したりするデモがなされ、AI Assistant の使い方を見せつつ、ユーザー視点での 「使いやすさ」 を意識した構成になっています。
実際の文章を素材にしながら、操作ガイド的な字幕/ポップアップ解説を重ねる手法を採用しており、リアルな操作感が伝わります。
とくに、ユーザー側が迷いそうな操作部分をナビゲーションしている工夫は、紹介動画でも安心感を与える効果があります。
5.「要約」のAIは、「要約」のためだけじゃない|ELYZA ブランドムービー
このブランドムービーは、ELYZA が “要約” の AI 技術を中心軸に据えつつ、その先にある「理解援助」「視点拡張」といった可能性を語る内容になっています。
動画はストーリー性重視で、技術紹介というより思想や理念を伝える形ですが、サービス紹介を検討する人にとっては、“要約” という機能を出発点として、どのように拡張性を語るかの見本になります。
映像のテンポ、語り口、技術的要素とのバランスを取る演出が参考になるでしょう。
まとめ
本稿で紹介した5本の動画は、それぞれ AI サービスの 「見せ方」 に異なる工夫を凝らしています。
「おもてなしQRメーカー」は更新運用性、「Slack AI」は UI への自然な埋め込み、「IVRy」は通信フローの可視化、「Adobe Acrobat」は実ドキュメント操作、「ELYZA」は機能の思想展開」といった具合です。
動画を作成する際には、単に “機能を列挙する” にとどまらず、ユーザーが「これで何ができるか」「導入すると何が変わるか」を直感的に掴める構成を意識することが重要です。